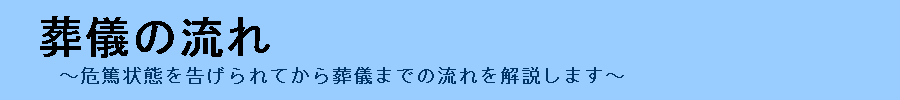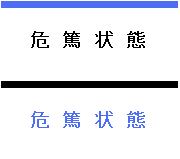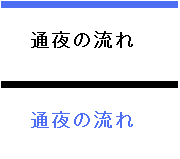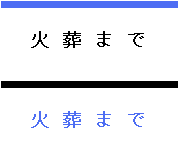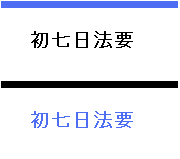●●●火葬まで●●●
【火葬】
日本では原則として死後24時間以内は火葬してはなりません。
火葬を行うには死亡届等を受理した市町村長の許可が必要であり、許可を受けずに火葬した
場合は法律違反となり、死体損壊罪に問われる可能性もあります。
【お別れの儀】
告別式が終わると、故人との最後のお別れをします。
棺のふたを開けて皆で祭壇に飾られていた供花の花を順に入れていきます。
これを「お別れの儀」といい、花のことを「別れ花」といいます。
顔の周りは白い花で、体の方は色のついた花を入れます。
【くぎ打ち】
棺のふたを閉じるのに、浄土真宗以外の宗派ではくぎ打ちの儀式が行われます。
三途の川の小石と言われる小石で釘を二度軽く打ちます。
棺の運び出しは遺族や近親者の男性が行います。
【火葬場】
火葬場についたら火葬許可証を提出して火葬をします。
火葬許可証を火葬場に提出すると火葬が終わった後、火葬許可証に日時を記入して係員が
捺印してくれ、これが埋葬許可証になります。
埋葬許可証は墓地に埋葬するのに必要になり、埋葬許可証が無いと埋葬できません。
棺は炉の前に置かれて納めの儀が行われます。
火葬にかかる時間は火葬場によっても違いますが1時間くらいです。
その間は控え室で待つことになります。
【拾骨】
荼毘に付したあと、火葬した骨を骨壷に納める骨あげを行います。
箸を使い喪主から順番に骨壷に納めていきます。
箸を使うのは故人をあの世へ「はし渡し」をするという意味からです。
足の骨から上半身の方へ向かって拾っていきますが、のど仏だけは一番最後に故人と最も
繋がりの深い遺族二人が拾って納めます。
のど仏は仏が坐った姿に似ており、仏様が宿っていると考えられているからです。